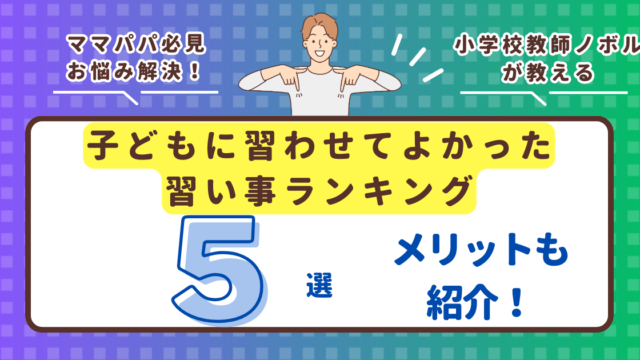こんにちは。ノボルです🧗今回は、「習いごとをサボっていたらどうする?」と題して書きます。
結論から言うと、「サボっていることを見つけたら、すぐに辞めさせるのではなく、子どもの思いを聞く、そして話し合う」です。
1.親のスタンスについて

自分から「やりたい!」と言い出したのに、しばらくすると練習をサボるようになり、「だったら辞めなさい!」「嫌だ!」という親子喧嘩になってしまうこともありますよね。
子どもがダラダラしてしまうのには、いくつかの理由が考えられます。マンネリによる飽きか。伸び悩みによる逃避か。生活リズムの狂いによる無気力か。やめたいと思っていても、うまく言い出せないのか。
親がどんなスタンスに立つかによって、今後の捉えに影響すると私は思います。この時はダラダラと叱るのではなく、理由を聞いてみるべきで、またその原因に目を向けるべきだと思います。
親はすぐに結果を求めがちなので、「結果が出ないこと=ダラダラしている」と決めつけるのはよくありません。
2.例 スランプで落ち込んでいる場合は?
スランプで、落ち込んでいるのなら「これまで頑張ってきたからこそ、悔しい思いをしているのだね」と寄り添う姿勢を見せ、褒める。
そして、誰でも必ず挫折やスランプを経験し、その逆境を乗り越えないと成長できないことを説明する。(説教じみたものにしないこと)
親自身のエピソードや体験談を話すと、子どもはイメージしやすくなり、効果的です🎯
また習いごとには一生懸命でも、学校や勉強が疎かになるケースもあります。親は不安で「習いごとをやめなさい」と言いたくなるものです。
また、反対に「お前は習いごとだけでよくて、勉強なんかしなくていい」と言い放つ親もいます。
しかし、勉強と習いごとは二者択一のものではありません。習いごとでの成功が後に勉強でもプラスに働くことだってあります。
学校の成績が良くないからと親が無理に押さえつけて勉強させても、どちらも中途半端になる最悪の状態になりかねません。
なぜ成績が伸びないのか。生活習慣など、習いごと以外の家庭教育的側面からの原因を解明すべきだと思います。
3.まとめ
どちらかが良いとか悪いではなく、あくまで一面的に見ることなく、子どもと話し合って決めることです。👦子どもと一緒に話し合った中で、子どもも納得した形になっていると、次の一歩が踏み出しやすくなります。しかし、話し合いをせず一方的に続けたり辞めさせたりすると、能力だけでなくメンタル面での成長も止めてしまいかねません。
必ず参加するものではなく、時間とお金を費やす習いごとだからこそ、じっくりと目標を見据えてとりくんでいけたらいいですね。
以上、「【習いごと】習いごとをサボっていたらどうする?」という話題でした。
ほいじゃあね~👋
〜前向きにしてくれる言葉〜
できるかどうか
を考えると心配になる
やりたいからやる
と思えば楽しくなる